【2025年】建築基準法改正で何が変わる?変更点と重要ポイントを解説
最終更新日:2025/07/24
業界トレンド

建設テックの知恵袋 編集室
業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

2025年4月に施行された建築基準法改正は、建築業界に大きな影響をもたらしました。
この改正によって新たな規制や基準が導入され、建築物の安全性や環境性能が向上する一方で、手続きやコストの増加が懸念されます。
また、中には改正箇所が多く「いまいち変更点がわからない」「どう対応すべきかわからない」とお困りの方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、2025年建築基準法改正によって変わる内容や、ポイントをわかりやすく紹介します。
【目次】
建築基準法について

建築基準法は、日本国内で建物を建築・利用する際に守らなければならないルールを定めた法律です。1950年に制定され、国民の生命・健康・財産を守ることを目的としています。
建築基準法は戦後の急速な都市化と人口増加の中で、建物の安全性や都市環境の整備を図るために制定されました。
制定されて以降も、耐震基準の強化やバリアフリー化、省エネ基準の導入など、社会の変化に応じて何度も改正されています。建築基準法が改正されることにより、建物の構造や仕様などに関する基準の一部にも変化が生じます。
また、施行日以降に建築確認を申請する建築物は、新たな基準に適合させなければなりません。
2025年建築基準法改正で押さえておきたいポイント

2025年建築基準法改正では、業界に大きな影響を与える変更がいくつか行われています。
ここでは、建築基準法改正で押さえておきたいポイントを解説します。
4号特例の縮小
建築基準法改正に伴い、4号特例の対象範囲が大幅に縮小され、従来の4号建築物は「新2号建築物」「新3号建築物」などに再編されます。
そもそも4号特例とは、以下に該当する小規模木造建築物などを対象に、構造審査や一部の検査を省略できる制度です。
- 2階建て以下
- 延べ500㎡以下
- 高さ13m以下
- 軒高9m以下
この特例では、小規模な住宅の新築やリフォームがスムーズに進められる一方、耐震性や安全性が十分に確認されないまま建築されることもありました。
建築基準法改正により、これまで特例の対象だった建物の多くが、今後は構造審査や建築確認の対象となります。
これにより建物の安全性は高まりますが、設計段階での構造図書の提出や審査が必要となるため、設計者の負担は増加します。
出典:国土交通省:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
省エネ基準適合の義務化(建築物省エネ法との連携)
建築基準法改正によって、2025年4月からすべての新築住宅・非住宅建築物に対し、省エネ基準への適合が義務化されています。
これまでは主に中・大規模建築物が対象でしたが、改正によって小規模住宅も含めた全建築物が対象となりました。届出義務・説明義務に留まっていた建築物も、基準適合が必須となるため、施主への丁寧な説明と合意の形成が必要です。
なお、増改築の場合は、増改築部分のみが省エネ基準に適合していれば問題ありません。
出典:国土交通省:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
大規模木造建築物の防火規制緩和
今回の建築基準法改正では、大規模木造建築物の防火規定が大きく見直されました。
これまでは延べ面積3,000㎡を超える木造建築物では、主要な木造部を不燃材料で覆うか、または3,000㎡ごとに耐火構造体で区画する必要がありました。
改正後は、火災後に周囲への危害を防ぐ措置を講じることで、柱や梁などの構造木造を「現し」として露出させる設計が可能です。
これにより、木材の温かみを活かしたデザインの自由度が大幅に向上します。
構造規制の合理化
2025年の建築基準法改正では、木造建築物を中心に構造安全性の確認方法や基準が見直されています。
改正前と改正後のポイントについて以下の表にまとめています。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 簡易構造計算で建築可能な範囲 | 高さ13m以下・軒高9m以下 | 階数3以下かつ高さ16m以下 |
| 構造計算が必要な木造建築物の規模 | 延べ面積500㎡超 | 延べ面積300㎡超 |
| 設計者の資格制限 | 高さ13m超・軒高9m超は一級建築士のみ | 階数3以下・高さ16m以下は二級建築士も設計可能 |
改正前の建築基準法は、高さ13m(軒高9m)を超える木造建築物に、詳細な構造計算を課していました。また、一級建築士でなければ設計や工事監督ができない規制もありました。
改正後は、3階以下かつ、高さ16m以下までの木造建築物は簡易な構造計算で建築可能となり、二級建築士も設計を手がけることができます。
ただし、構造計算が必要な延べ面積については、これまでの500㎡から300㎡に変更されており、縮小されています。
既存不適格建築物への規制一部免除
建築基準法改正によるポイントとして、既存不適格建築物への規制一部免除があります。
これは建築当時は合法だったものの、そのあとの法改正で現行基準に適合しなくなった建物について、一定の条件下で現行基準のすべてを適用しなくてもよいとする特例措置です。
従来、建物を修繕やリノベーションするためには、現行の建築基準法に完全に適合させる必要がありました。
そのため、接道義務や防火規定などの違反があると改修自体が困難で、空き家の再利用や耐震改修が進まない要因となっていました。
今回の改正では、市街地環境に大きな影響がないと認められる場合に限り、現行基準の一部適用を免除できるようになっています。
2025年建築基準法改正とその背景

2025年建築基準法は、環境配慮や建物の安全性の確保などを目的としています。
ここでは、法改正の背景を解説します。
カーボンニュートラルの実現と地球温暖化対策
今回の建築基準法改正は、2050年カーボンニュートラルと地球温暖化対策を強く意識した内容です。
日本は、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を国際公約としています。さらに2030年度までに2013年度比で温室効果ガスを46%削減する目標も掲げています。
この目標達成のためには、建築物の断熱性向上や設備の省エネ化など、建築分野におけるエネルギー消費削減が不可欠です。
そのため、2025年の建築基準法改正では、省エネ基準への適合が義務化されています。
木材の利用促進
木材の利用促進も、建築基準法改正が行われた理由の一つに挙げられます。
木造建築物は、製造時の二酸化炭素排出量が鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べて少なく、環境負荷が低い建築方式です。また、木材利用の拡大は、建築分野の二酸化炭素排出だけでなく、地域産材の活用や林業振興、資源の循環利用にもつながります。
このような背景もあり、2025年の建築基準法改正では、大規模建築物の木造化や防火規定の見直しなど、木材利用を推進するための制度改正が行われました。また、木材の利用促進は、カーボンニュートラルの実現や地球温暖化対策にも一定の効果が期待されます。
建物の倒壊防止
2025年の建築基準法改正が行われた理由として、「建物の倒壊防止」も挙げられます。
これまで4号特例により構造計算や建築確認審査が省略されていた構造物について、地震や気象災害時における倒壊リスクが検証されていないという課題がありました。
このため、今回の建築基準法改正では、4号特例の対象範囲を縮小し、従来よりも多くの木造住宅や小規模建物で構造計画書の提出や審査が義務化されています。
2025年建築基準法改正の課題
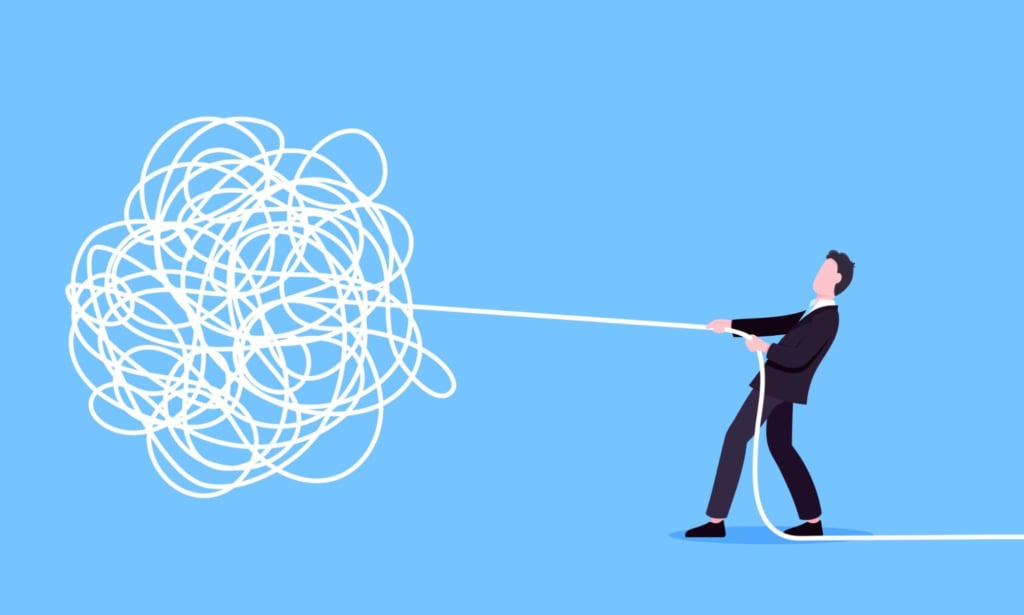
2025年建築基準法改正は消費者にとってはメリットが多くありますが、業者側には負担や課題が増えます。
ここでは、法改正によって生じる課題を解説します。
業務負担の増大
建築基準法が改正されたことで、建設業界では業務負担の増大が懸念されています。
なぜなら、これまで確認申請や構造計算が不要だった小規模建築物も、改正後は申請や構造計算が必要となり、設計者や施工業者の業務量が増えるためです。
また、各種図面や構造関連資料の作成や提出も求められ、書類作成の手間や整合性の確認にも時間がかかります。業務負担の増大によって人材確保や体制の見直しなど、さまざまな対応が必要となります。
コスト負担の増大
コスト負担も、建築基準法改正で懸念される課題の一つです。
省エネ基準適合の義務化により、断熱材や高性能窓、省エネ設備の導入が必要となり、材料費や設備費が上昇します。さらにこれまで省略されていた確認申請や構造計算などにかかる費用も増加します。
また、発注者側の予算や事業採算の都合もあり、増加したコストのすべてを価格転嫁できるとは限りません。価格を上げてしまうと受注が減ったり、競合との価格競争が激化したりなどのリスクもあります。
工期の長期化
建築基準法改正により、工期の長期化も懸念されています。
なぜなら、これまで省略されていた確認申請や構造計算の義務化により、設計や申請、審査にかかる時間が増えるためです。また、行政による審査も厳格化されており、申請から許可を得るまでの期間が長くなるケースが増えています。
さらに、工期の長期化には以下のリスクがあります。
- 建築コストの増加
- 人件費の増加と人手不足の悪化
- 設備投資や事業計画への遅れ
工期の長期化はコスト増加や経営リスクの増加など、さまざまな悪影響を及ぼします。
法改正への対応の遅れ
2025年の建築基準法改正では、改正内容が多岐にわたるため、現場や関係者の対応の遅れが懸念されています。
これまで経験のなかった省エネ計算や追加資料の作成も必要となり、設計者や施工業者は新たなスキルや知識の習得が必要です。
対応が遅れると、建築確認申請で不備や差し戻しが増え、着工や引き渡しの遅延、最悪の場合は契約キャンセルや事業の見直しにもつながります。
その他、今後建設業界で懸念されている課題や解決策について以下の記事でも詳しく解説しています。
⇒【2025年以降】建設業界における今後の課題と解決策!人材確保に向けた具体的な戦略
まとめ
2025年の建築基準法改正により、省エネ基準の義務化や4号特例の縮小が進み、申請業務や工期、コストの負担が増加しています。
今後はこれらの法改正に迅速かつ的確に対応し、業務効率を高めるための対策がますます重要となります。現場の生産性向上や工期の適正化、法令順守の徹底が、今後の建設プロジェクトの成功のカギとなるでしょう。


