労働安全衛生法をわかりやすく解説!重要な目的と労働基準法との違いを知ろう
最終更新日:2025/07/22
工事現場の基礎知識

建設テックの知恵袋 編集室
業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!
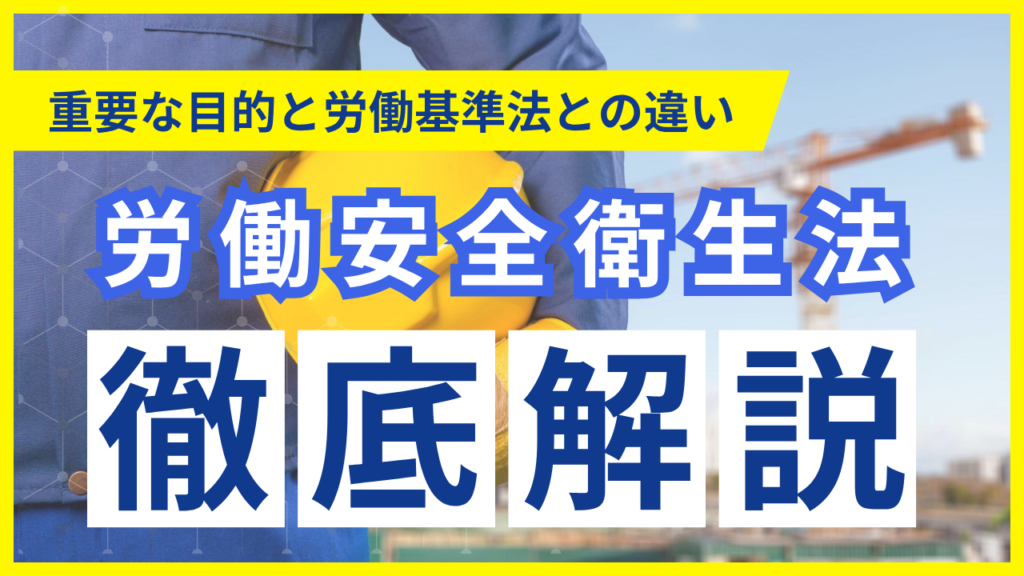
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を実現することを目的とした法律です。
特に建設業では、高所での作業や重機の操作など、危険を伴う業務が多く発生します。そのため、労働災害のリスクを低減するために、厳格な安全対策や管理体制の整備が求められています。
一方で、「労働安全衛生法は聞いたことがあるけど内容がいまいちわからない」「労働基準法との違いがわからない」という方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、労働安全衛生法についてわかりやすく解説し、その目的や労働基準法との違いも紹介します。
【目次】
- 労働安全衛生法とは
- 労働安全衛生法の対象
- 建設業で労働安全衛生法が重視される理由
- 労働安全衛生法に定められた事業者の義務
- 労働災害リスク低減と生産性向上につながるリソース管理アプリ『Photoruction Site』
- まとめ
労働安全衛生法とは

労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するために定められた法律です。
ここでは、労働安全衛生法について詳しく解説します。
労働安全衛生法の概要
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守るために、事業場ごとに安全衛生管理体制の整備や、労働災害防止のための具体的な措置を定めている法律です。
この法律では、事業者に対して以下の総合的かつ計画的な対策を求めています。
- 労働災害防止のための危害防止基準の確立
- 責任体制の明確化
- 自主的な安全衛生活動の促進
単なる事故防止だけでなく、快適な職場環境づくりや健康維持にも重点を置いています。また、労働者自身も災害防止のために必要事項を守り、事業者の安全衛生措置に協力する責任が課されています。
出典:e-GOV法令検索:労働安全衛生法、厚生労働省:安全・衛生
労働安全衛生法が制定された背景
労働安全衛生法は、働く人々が安心して健康的に仕事ができるように、職場の安全や衛生環境を整えるために1972年に制定されました。
当時は高度経済成長期であり、工場や建設現場で多くの人がケガや命を落とす事故が多発していました。
こうした深刻な労働災害を減らすために、労働安全衛生法が制定され、その後も時代に合わせて改正されながら職場の安全と健康を守るために重要な役割を果たしています。
また、国土交通省の「建設業における安全衛生をめぐる現状について」によると、労働安全衛生法が制定されて以降、労働災害による死傷者数は減少傾向にあります。
労働安全衛生法の対象
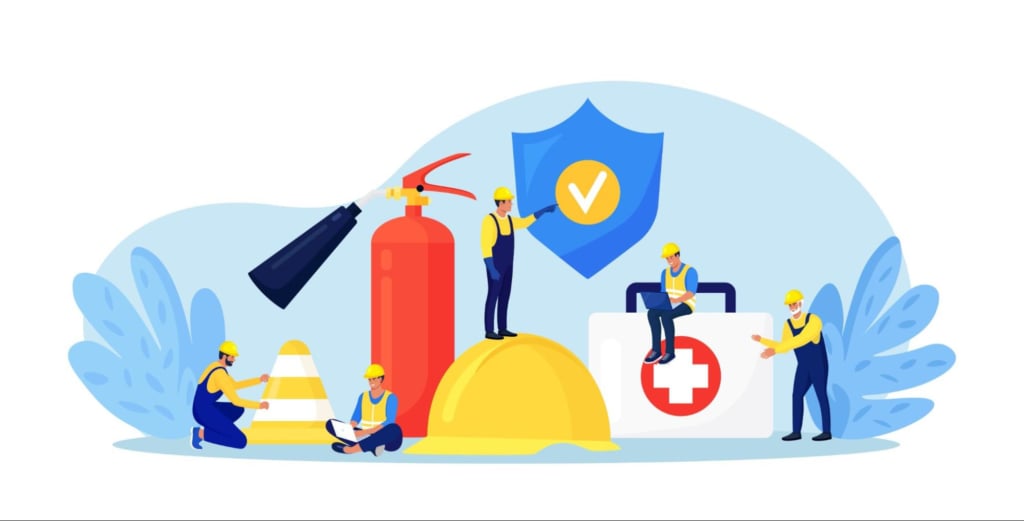
労働安全衛生法の対象となるのは、事業を営み労働者を雇用する事業者と、その事業者に雇用され賃金を受け取る労働者です。
これは個人事業主・法人を問わず、労働者を雇用する事業者が対象です。
また、2025年4月1日施行の改正労働安全衛生規則により、危険箇所で作業する他社作業員や一人親方等に対しても一定の安全措置を講じる努力義務が課されます。
これにより、雇用の有無にかかわらず、現場で作業するすべての人が一部の安全措置の対象となっています。
労働基準法との違い
労働基準法と労働安全衛生法はどちらも労働者を守る法律ですが、目的と役割が異なります。
労働基準法は、賃金や労働時間、休日など、働くうえでの最低限の労働条件を規定し、労働者の権利を守ることが目的です。
以下の表に、労働基準法と労働安全衛生法の違いをまとめています。
| 労働安全衛生法 | 労働基準法 | |
|---|---|---|
| 目的 | 労働者の安全と健康を守り、職場環境を整える。 | 労働条件の最低基準を定め、労働者を保護する。 |
| 内容 | 職場の安全衛生管理健康診断労働災害の予防など安全・健康・職場環境に関する基準を規定。 | 賃金労働時間休日休憩有給休暇など労働条件全般の最低基準を規定。 |
| 罰則の有無 | あり | あり |
なお、労働基準法は1947年に制定された法律ですが、当時はこの法律内に現行の労働安全衛生法に関する規定が含まれていました。
しかし、高度経済成長期に労働災害が多発したことで、専門的かつ総合的な安全衛生対策が必要となったため、労働安全衛生法として新たに制定されました。
建設業で労働安全衛生法が重視される理由

建設業では労働安全衛生法が重視されており、事業者は労働者の安全や健康を守るために、さまざまな業務を負っています。
ここでは、建設業で労働安全衛生法が重視される理由を解説します。
労働災害のリスクが高い
建設業で労働安全衛生法が重視される理由は、労働災害のリスクが高いためです。
建設現場では、高い場所での作業や重いものの運搬、不安定な足場など、危険な作業が必要となります。そのため、墜落や転落、重機との接触事故が発生しやすく、労働災害が起こりやすくなっています。
このような特性もあり、建設業では事故を防ぐための厳格な安全管理が求められているのです。
健康被害のリスクがある
建設業で労働安全衛生法が重要となるのは、健康被害のリスクを減らすことも理由です。
建設現場では重量物の運搬や粉じん、有害物質の取り扱いなど、事故だけでなく長期的な健康被害につながる要因が多くあります。
例えば、粉じんや有害な化学物質を吸い込むことにより、呼吸器系の病気になるリスクが高まります。また、騒音による難聴や振動工具による振動障害など、建設業特有の健康障害があるのも特徴です。
こうした健康被害を防ぐためにも、労働安全衛生法の遵守が必要となります。
法律による安全管理の義務化に対応するため
法律によって安全管理が義務化されていることも、労働安全衛生法が重視される理由の一つです。
建設現場では危険な作業が多く、それに対応する安全管理が法律で義務付けられています。例えば、一定規模以上の現場になると、事業者は現場ごとに安全管理者や衛生管理者、産業医を選任し、安全衛生委員会を設置しなければなりません。
こうした法律による安全対策の義務化が、建設現場における安全衛生対策を徹底する大きな要因となっています。
労働安全衛生法に定められた事業者の義務

労働安全衛生法では、事業者にさまざまな義務が課されています。
ここでは、労働安全衛生法に定められた事業者の義務を解説します。
安全衛生管理体制の構築
労働安全衛生法では、事業者に対して安全衛生管理体制の構築を義務付けています。これは、労働災害を防ぎ、労働者が安全で快適な環境で働けるようにするためです。
安全衛生管理体制とは、現場ごとに必要な管理者を設置し、権限や責任、役割を明確にする体制を指します。
事業者の規模や現場状況によって異なりますが、以下のような管理者が選任対象です。
- 総括安全衛生管理者
- 安全管理者
- 衛生管理者
- 産業医
- 安全衛生推進者・衛生推進者
- 店社安全衛生管理者
- 統括安全衛生責任者
- 作業主任者
これらの管理者は、現場の安全・衛生の確保、健康診断や教育の実施などに対応するために重要な役割を担っています。
安全衛生委員会等の設置
建設業において労働安全衛生法は、50人以上の労働者を使用する現場では、安全衛生委員会等の設置を義務付けています。
安全衛生委員会は、現場の安全衛生に関する重要事項を審議し、労働災害防止や健康障害防止のための方策を協議する場です。
また、安全衛生委員会は毎月1回以上開催し、議事内容を労働者に周知し、議事録を3年間保管する義務があります。
出典:厚生労働省:安全委員会、衛生委員会について教えてください。
危険・健康障害の防止措置
建設業において労働安全衛生法が定める危険・健康障害の防止措置は、現場で発生しうる事故や健康被害を未然に防ぐために事業者が講じるべき対策です。
具体的には、以下のような措置を行う必要があります。
- 高所作業では手すりや安全ネットを設置する
- 落下物防止のための防網や立入禁止区域の設定を行う
- 粉じんや有害な化学物質を扱う現場では換気設備と保護具を用意する
- 機械や設備には安全装置を設置し、定期的に点検と整備を行う
- 定期的に健康診断を実施する
これらの措置を怠ると、労働災害や健康障害のリスクが高まるだけでなく、法令違反として厳しい罰則の対象となる可能性もあります。建設業の事業者は、現場ごとに適切な危険・健康障害防止策を徹底することが求められます。
出典:e-GOV法令検索:第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
リスクアセスメント
労働安全衛生法では、事業者にリスクアセスメントの実施を義務づけています。
リスクアセスメントとは、現場で発生しうる危険や有害の要因を事前に洗い出し、それぞれのリスクの大きさを評価したうえで必要な安全対策を講じることです。
具体的には、作業前に現場の危険性や有害性を調査し、評価結果に基づいて、リスクの高い作業や場所に安全対策を実施します。労働者に対しては、リスクアセスメントの内容や安全対策を周知します。
また、リスクアセスメントの結果や対策内容は記録し、必要に応じて見直しも行わなければなりません。
安全衛生教育
建設業では、労働安全衛生法に基づき、安全衛生教育の実施が事業者の義務とされています。安全衛生教育とは、労働者が業務に従事する際に必要な安全や衛生に関する知識を身につけさせ、労働災害を防止するために実施される教育です。
法律により、事業者は労働者を雇い入れたときや作業内容が変更された際、危険な業務に従事させる場合に、所定の安全衛生教育を実施する義務があります。
安全衛生教育の内容は、機械や原材料の危険性、保護具や安全装置の使い方、作業手順、応急措置など多岐にわたります。
出典:e-GOV法令検索:第六章 労働者の就業に当たつての措置
快適な職場環境の形成
労働安全衛生法において、事業者には快適な職場環境の形成に努める義務があります。
具体的には、作業環境の温度、湿度、換気、照明、騒音、休憩施設、トイレの整備などです。これは努力義務であるため法的制裁の対象とはならないものの、継続的かつ計画的に職場の環境改善に取り組むことが望ましいとされています。
また、疲労やストレスが生じにくい快適な職場環境を整えることは、労働者のモチベーションを高めたり、求職や離職防止につながります。
出典:e-GOV法令検索:第七章の二快適な職場環境の形成のための措置
健康診断の実施
労働安全衛生法では、健康診断の実施を事業者に義務付けています。
事業者は常時使用する労働者に対し、年1回以上の定期健康診断を実施しなければなりません。雇入れ時や特定業務に従事する労働者には、雇入れ時の健康診断や特殊健康診断が必要です。
健康診断の結果は5年間保存し、常時50人以上の労働者を使用する事業者では、労働基準監督署への報告義務もあります。
なお、健康診断の費用は法令により、常時使用する労働者に対しては、事業者が全額負担して実施することが義務付けられています。診断で異常が見つかった場合には、産業医の意見を聞き、必要な就業上の措置を講じなければなりません。
ストレスチェックの実施
ストレスチェックの実施も、労働安全衛生法で義務付けられていることの一つです。
これは労働者の心理的な負担の程度を把握するために、医師や保健師などが年1回以上実施する検査です。主に50人以上の労働者を使用する事業場で義務付けられており、質問票に記入する形で行われます。
実施の目的は、労働者自身がストレスの状況に気づき、メンタルヘルス不調を未然に防止することです。検査結果は本人に通知され、希望者には医師による面接指導が行われます。
出典:厚生労働省:ストレスチェックに関する法令
労働災害リスク低減と生産性向上につながるリソース管理アプリ『Photoruction Site』
労働安全衛生法で定められた義務を果たし、現場の安全管理や関連書類管理を効率化するためにはクラウド型の管理システムがおすすめです。
『Photoruction Site(フォトラクションサイト)』は、建設現場の安全管理や関連書類の作成・管理を効率化するクラウド型の管理システムです。
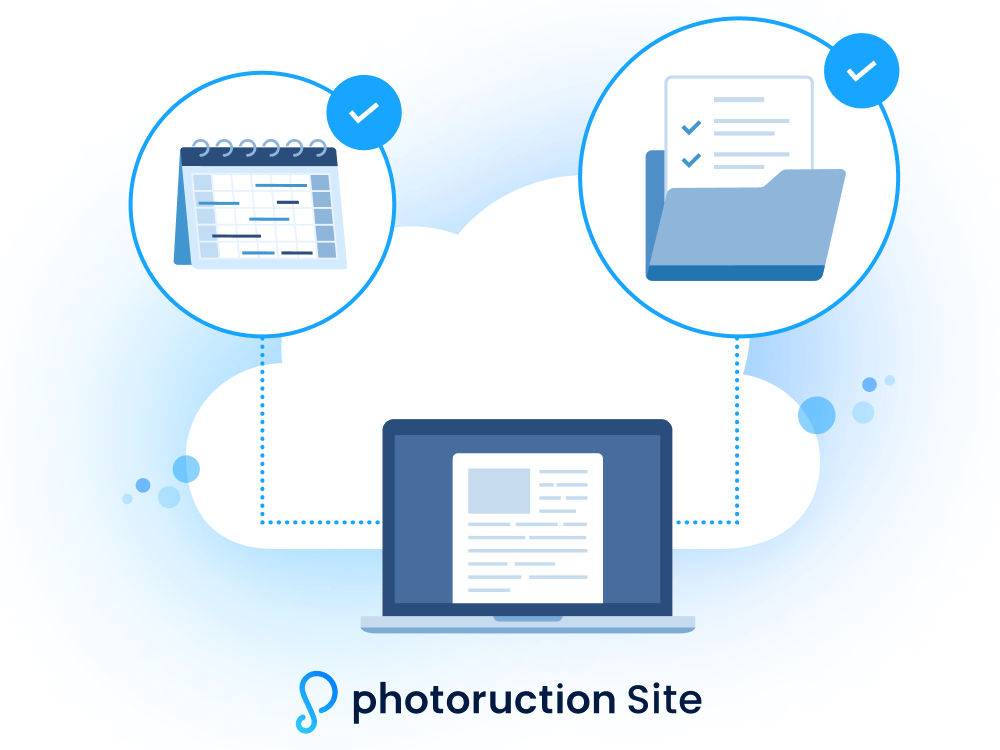
労働安全衛生法で義務付けられている各種安全書類をクラウド上で一元管理し、法令違反や労務トラブルのリスクを減らすことができます。
また、工事写真や図面、進捗状況などもデジタル端末から簡単に記録・共有できるため、現場の安全管理や作業内容の見える化が可能です。これにより、情報伝達のミスやヒューマンエラーを防ぎ、現場全体の安全レベルの向上と生産性向上に寄与します。
このように、クラウド型の管理システムがあれば法令遵守と現場の安全性・効率性を両立し、働く人の安心・安全な環境づくりにもつながります。
まとめ
労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守るために定められた重要な法律です。
建設業においては特に厳格な安全管理が求められ、事業者はさまざまな対策を講じなければなりません。特に現場の安全対策や書類管理の効率化は重要な課題となります。
クラウド型の管理システム『Photoruction Site(フォトラクションサイト)』を活用することで、法令遵守と現場の効率化を両立でき、労働災害リスクの低減や生産性向上、快適な職場環境の実現につながります。
無料デモもあるため、まずは無料ダウンロードできるサービス紹介資料をぜひご覧ください。


