建設業法の見積期間とは?数え方や注意点をわかりやすく解説
最終更新日:2025/09/25
施工管理ハック

建設テックの知恵袋 編集室
業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!
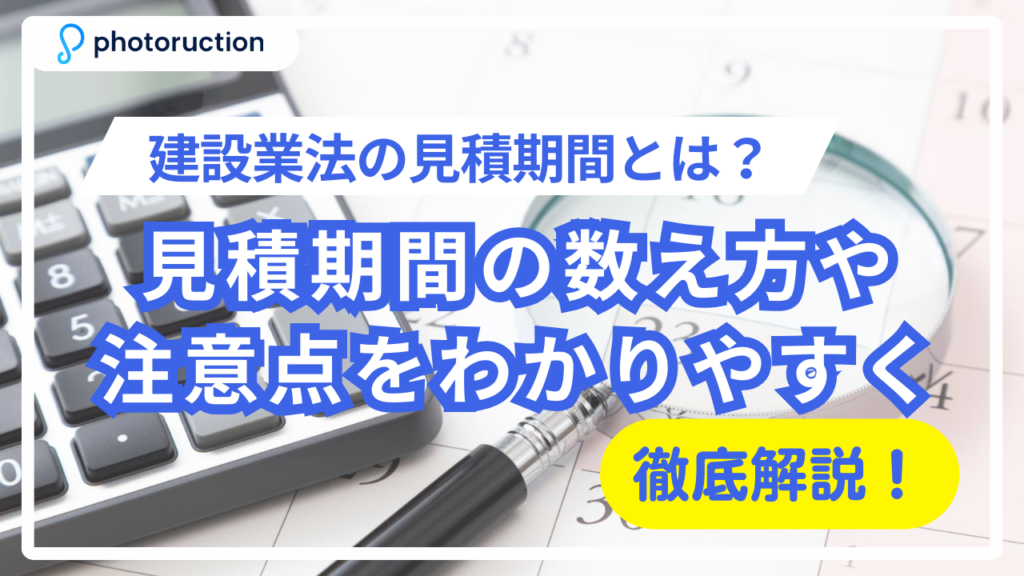
建設業法における見積期間は、発注者が建設業者に見積依頼をした際、見積書を正確かつ適切に作成・提出するための期間を法令で定めたものです。
発注者は見積依頼時に期間を示し、建設業者はその期間内に見積書を提出する義務があります。中には、「見積期間の数え方がわからない」「何か注意点はある?」など疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、建設業法の見積期間の概要や数え方、注意点を紹介します。
【目次】
見積期間の概要

建設業法では見積期間が設けられています。
ここでは、見積期間の概要や法的意義と目的、建設業者が確認すべきポイントを解説します。
建設業法における見積期間とは
建設業法の見積期間とは、発注者が建設業者に工事見積の依頼をした際に、建設業者が見積書を作成・提出するために必要な最低限の期間です。
これは契約書の公正を確保し、建設業者が十分な時間を持って正確な見積を作成できるように法令で定められています。
見積期間は工事の請負金額に応じて異なり、規模の大きな工事になるほど長く設定されています。
見積期間の法的意義と目的
見積期間の法的意義は、発注者が建設業者に対して見積作成のため最低限の時間を保障し、不当に短い期間での見積要求を禁止することにあります。
これにより建設業者は急かされることなく、工事内容や費用の詳細を検討し、適正で透明な見積書の作成が可能です。建設業法で見積期間を明示することで、契約の公正性を確保し、契約トラブルや法令違反を未然に防止します。
見積期間の設定は、発注者・受注者双方の権利保障と信頼関係構築を目的とした重要な枠組みです。
見積依頼時に建設業者が確認すべきポイント
建設業者が正確な見積書を作成するためには、発注者から具体的かつ詳細な情報を受け取ることが不可欠です。
以下の項目は特に重要であり、正確な見積作成とスムーズな契約締結に直結します。
| 項目名 | 内容の例・ポイント |
|---|---|
| 工事の規模・内容 | 工種、工事範囲、施工条件など |
| 設計図面・仕様書 | 図面の有無、仕様の詳細、設計変更の有無など |
| 工期・納期 | 着工予定日、完了期間、スケジュール目安など |
| 見積期間の明示 | 建設業法に基づく法的期間の明示 |
| 支払い条件 | 支払い時期、方法、条件など |
| 品質・安全要件 | 使用材料の品質基準、安全対策の有無など |
| 特殊条件 | 特殊施工、周辺環境対応、許認可の要否など |
発注者からこれらの情報を的確に受け取ることにより、見積の透明性と信頼性が高まり、双方の認識のズレや後のトラブルを未然に防止できます。
また、正確な見積作成のためには、発注者と十分に情報共有・確認を行うことが重要です。
見積期間の法定期間

建設業法では、工事の請負金額に応じて見積期間の最低日数が法定されています。
ここでは、見積期間の法定期間について解説します。
請負金額別の見積期間の最低日数
建設業法により、工事請負金額に応じた見積期間の最低日数は、建設業法施行規則により次のように定められています。
| 工事請負金額 | 見積期間の最低日数 |
|---|---|
| 500万円未満 | 1日以上 |
| 500万円以上5,000万円未満 | 10日以上(短縮時は5日以上) |
| 5,000万円以上 | 15日以上(短縮時は10日以上) |
請負金額別の見積期間の最低日数は、工事の規模と複雑さに応じて異なり、大きな工事ほど詳細な検討が必要なため長い期間を設ける必要があります。
このため、500万円未満は1日以上、500万円以上5,000万円未満は10日以上、5,000万円以上は15日以上と区分されています。
見積期間短縮の条件
建設業法では見積期間の短縮は、工事の予定価格が500万円以上の場合に限って、やむを得ない事情がある時のみ認められています。
この短縮は例外的措置であり、通常の契約では適用されません。
やむを得ない事情とは、例えば自然災害による急な復旧工事や行政の事情による発注の遅延などが想定されます。
ただし、明確な基準は定められていないため、短縮を行う際は発注者と受注者の合意と行政への確認が必要です。
不当な短縮は法律違反のリスクを伴うため、慎重に対応することが求められます。
見積期間の数え方

建設業法では見積期間の数え方も厳密に決められているため、正しくカウントする必要があります。
ここでは、見積期間の数え方を解説します。
見積期間の開始日
見積期間の開始日は、発注者が建設業者に見積依頼をした翌日からカウントを始めることが法律で定められています。
見積依頼当日は期間に含まれず、翌日が1日目となる点に注意が必要です。
例えば、4月1日に依頼が行われた場合は4月2日が見積期間の初日となり、そこから暦日で見積期間を数えます。
建設業者はこの開始日を基準に見積書作成や資材調達などを計画しなければなりません。
土日や祝日を含めるかについて
建設業法に基づく見積期間は暦日でカウントされるため、土日祝日、年末年始などの休日も見積期間に含まれます。
営業日数でのカウントとは異なり、休日も除外せずに期間全体を連続した日数として計算するため注意しましょう。
例えば、建設業法に基づき10日間の見積期間が必要な場合に、4月1日に発注者が建設業者に見積依頼をしたとします。
この場合、見積期間の開始日は4月2日となり、そこから暦日で10日間数えるため、見積書の提出期限は4月11日(10日目)以降です。
見積期間に関する注意点

見積期間は建設業法で定められた重要な法定期間であり、いくつか注意点もあります。
ここでは、見積期間で気をつけたいポイントを解説します。
見積期間が短すぎる場合
建設業法で定められた見積期間よりも短い期間で見積依頼を受けると、建設業者は工事内容や費用を検討できず、正確な見積書を作成することが困難になります。
その結果、不利な条件で契約を結ばざるを得ず、業者の権利や利益が損なわれるリスクが高まります。建設業者は見積期間を正確に把握し、短すぎる要求には適切に対応することが重要です。
なお、見積期間の最低日数を守らないのは発注者側の違反行為であり、行政指導や罰則の対象となります。
やむを得ない短縮の場合も事情を明確にし、合意・行政確認を怠らないようにしましょう。
トラブル防止のためにも適正な見積を作成する
適正な見積作成を行うことは、工事契約上のトラブル防止に直結します。
法的な見積期間を把握し、十分な検討時間を設け、材料費・労務費など見積内容を明確にすることが重要です。また、発注者から受ける情報が不足していれば、必ず早期に確認し、曖昧なまま見積作成を進めることは避けましょう。
見積書は契約の根拠資料となるため、内容の正確性や透明性が後のトラブル防止につながります。
期日を守ることはもちろん、価格根拠の記載漏れや誤解を招く表現は控え、双方の認識が一致するように丁寧に作成します。
工事内容が変更になった場合
工事内容が変更になった場合、建設業者は新たな内容に基づき適正な見積書を再作成する必要があります。
内容変更によって工法や工期などが変われば、費用項目も大きく変動するため、最新の設計図面や仕様書の受領や確認を行います。加えて、見積期間も工事金額や希望に応じて法的日数を確保しなければなりません。
発注者の都合などで見積期間や内容が曖昧なまま進めてしまうと、後日トラブルや責任追及を招くリスクがあります。
工事内容が変更した際には、必要な情報を早期に取得し、見積期間の再設定や行政への確認を怠らないようにしましょう。
見積期間を守るためのポイントやコツ

見積期間を守るためには、業者として計画的な進行管理や情報収集、ITツールの活用が欠かせません。
ここでは、見積期間を守るためのポイントやコツを解説します。
見積作成スケジュールの計画と管理を徹底する
見積期間を守るためには、最初に納期から逆算したスケジュール管理と細かな進捗管理が不可欠です。
まずは受注内容を把握した時点で、以下のような必要な作業を洗い出します。
- 現場調査
- 数量積算
- 協力業者への再見積依頼
- 外注品の調達確認
- 社内承認
作業の洗い出しができたら、それぞれの締切や担当者を明確にし、見積期間に遅れが生じないように優先順位を決めます。
特に大型案件や特殊案件では、社内外の連携やタイムラグを見越した余裕のある日程調整が必要です。
また、受注獲得の競争が激しい中においても、容易な期間短縮には流されず、計画性を持った作業分担で納期順守を徹底しましょう。
不明点や追加情報は早期に確認・対応する
不明点や追加情報が生じた場合、すぐに発注者や設計担当者と確認・協議することは、見積精度と納期順守に重要です。
疑問や不明点を放置したままにしていると、作業の遅延や誤った積算、契約リスクにつながります。受領した資料の中身を早期に精査し、以下についてリストアップしましょう。
- 情報に不足がないか
- 仕様に曖昧な点がないか
- 数量や範囲の協議は必要ないか
不明点や疑問があればメール等の記録残る形でやりとりし、発注者側の回答期限も明示しておけば、トラブル時の責任も明確化できます。
また、回答遅れによる納期圧迫が生じた場合は、期日調整や正式な見積期間延長を依頼することが重要です。
まとめ
建設業法の見積期間は、請負金額に応じて最低1日から15日以上と定められています。
これは、業者が十分な時間をもって正確な見積書を作成できるよう保障するための法的枠組みです。見積期間の数え方は、発注日翌日から暦日で数え、土日祝日も含みます。
建設業者は、発注者から工事内容や支払い条件などの情報を早期に受け取り、適正な期間を確保して見積書を作成することが大切です。
また、不当な期間短縮には慎重に対応し、法令遵守を徹底することが求められます。
『Photoruction』は、書類作成から見積期間のスケジュール管理までトータルに支援するクラウド型施工管理アプリです。モバイル端末対応で書類作成やスケジュール通知・自動リマインド機能を備え、期限遵守と効率化を強力にサポートします。
まずは無料ダウンロードできるサービス紹介資料をぜひご覧ください。


