工事写真を撮り忘れたらどうなる?対策やリスク、防止方法を紹介
最終更新日:2025/05/12
施工管理ハック

建設テックの知恵袋 編集室
業界の生産性向上に貢献する。そんな情報を1つでも多く皆様に届けられるよう頑張ります!

工事を行うにあたって、進捗や完成までの工程を記録するために写真撮影が必要です。工事写真を撮り忘れてしまった場合、現場での撮り直しには時間や手間がかかり、すでに施工されて該当場所が撮影できないケースもあります。
工事写真は施工の完了を証明するための重要な証拠となるだけでなく、不測の事態への対応にも影響を及ぼすため注意が必要です。
この記事では、工事写真を撮り忘れた場合にどうなるかをはじめ、対策、リスク、防止方法を紹介します。
【目次】
工事写真について

工事写真は工事の着工から完成までの各段階の施工状況や過程を記録した写真です。
ここでは、工事写真について解説します。
工事写真の必要性
建設現場における工事写真は、工事の過程を記録するために重要です。
施工前の状態や施工の進捗状況、完成後の状況など、各工程の写真を撮影することによって工事の全体像が把握できます。
また、工事が適切に行われたかどうかや、工事で作った出来形の証明など、施工計画書や設計図どおりに作られたかを証明するためにも必要です。
その他、発注者や監督者への報告資料や、施工ミスが発生した場合の原因特定や対処にも使われます。安全対策の徹底を確認し、事故の防止にも役立つため、建築現場において写真の取り扱いは重要です。
工事写真の撮り方や整理方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
工事写真の義務について
公共工事では工事の進捗状況や品質を確認するために、法律や契約上の義務として工事写真の撮影が必要です。工事写真は着工前、施工中、完了後のそれぞれの段階で必要であり、これによって発注者は工事が適切に行われているか判断します。
義務となっている写真が不足していると、工事内容の証明ができずに、契約違反とみなされる可能性があります。
一方、民間工事では法律上の義務はないものの、契約や仕様書で定められている場合が一般的です。しかし、発注者とトラブルが生じた際に、工事写真がなければ工事内容の証明ができず、損害賠償や支払いトラブルに発展するリスクがあります。
そのため、民間工事や小規模工事においても工事写真を撮影して保管するのが一般的です。
工事写真を撮り忘れた場合の問題とリスク

工事現場において工事写真は重要な役割を果たしており、撮り忘れによってさまざまな問題やリスクが生じます。
ここでは、工事写真を撮り忘れた場合のリスクや問題点を解説します。
支払いの遅延や減額のリスクがある
工事写真の撮り忘れには、工事代金の支払い遅延や減額のリスクがあるため注意が必要です。
公共工事においては、国土交通省の定める『工事写真の撮影・管理基準』などに基づき、写真管理が義務付けられています。また、工事写真は完成検査や代金支払いの際の証拠にもなります。
工事写真がないと、発注者から「工事内容が確認できない」と判断され、工事代金の支払いが滞ることや減額される可能性もあるでしょう。
証拠不足で再施工が必要になる
工事写真を撮り忘れることにより、証拠不足で再施工が必要になるリスクがあります。
工事写真を撮り忘れると、工事の品質や進捗状況の把握ができないため、何をどのように施工したかの証明もできません。発注者は設計図どおりに作られているかどうか確認できないため、作り直しを求めることもあります。
作り直しが発生すると、工期の延長や余分なコストがかかることになります。
トラブルや問題の証拠として残らない
工事中に何らかの問題やトラブルが発生した場合に、工事写真がなければ証拠を提示することができません。
工事写真は工事中に何らかの問題が生じた際に、その状況を客観的に記録するために重要な証拠となります。
例えば、コンクリートで覆われる鉄筋や配管などは、後から確認できないため、施工時の写真が唯一の証拠です。工事後に発生した損傷について、工事写真があれば「工事業者のミスか」「工事完了時の状態はどうだったか」など証明できます。
これによって補修対応や責任分担がスムーズになり、受注側に落ち度がなければ、クレームから会社を守ることにもつながるでしょう。
一方、工事写真がなければ、発注者とのトラブルが発生した場合に正当に主張することが難しくなります。
信頼関係の低下
工事写真を撮り忘れると、発注者や監督者に対しての報告資料が不十分になり、信頼関係が低下するリスクがあります。
工事写真が不足すると、発注者や監督者は現場の状況を正確に判断できず、「本当に適切な工事が行われているのか?」という不安を持ちます。
信頼を失うことにより、追加説明や再提出、追加指示が増えるなど現場運営にも支障が生じるでしょう。
また、発注者からは「情報共有ができておらず、現場管理がずさん」と判断されてしまい、今後の契約や取引に悪影響が出る可能性もあります。
補助金の交付が認められない
補助金を受けて工事を行う際に、工事写真を撮り忘れると補助金の交付が受けられないため注意が必要です。
補助金の交付を申請する際には、着工前、施工中、完了後の写真を提出する必要があります。補助金の審査において、これらの写真に不備があると、補助金の交付が却下される可能性があります。
工事写真を撮り忘れた場合の対策
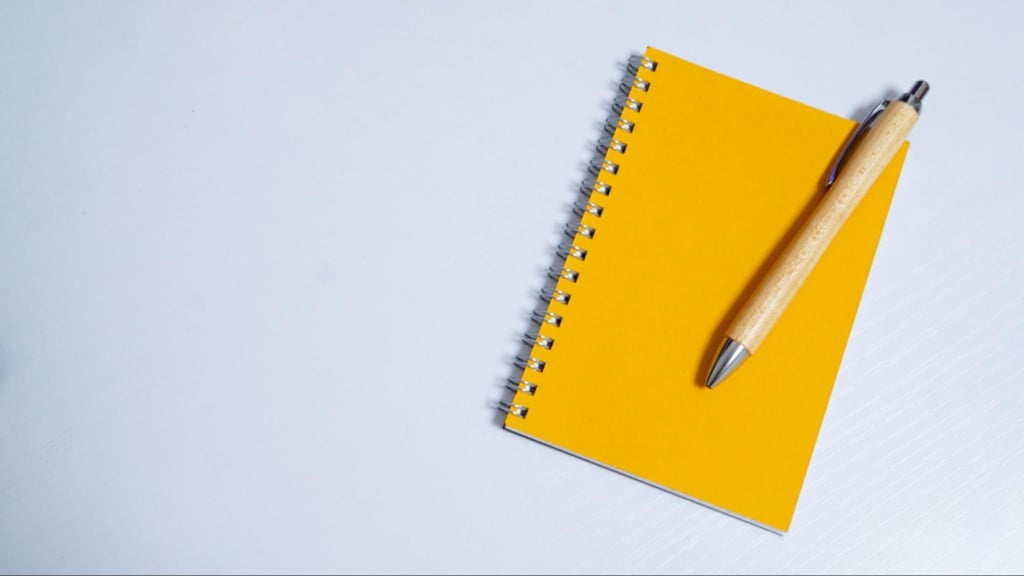
工事写真を撮り忘れてしまった場合、気づいた時点で、速やかに対応を行いましょう。
ここでは、工事写真を撮り忘れた場合の対策を紹介します。
できるだけ早く再撮影する
工事写真を撮り忘れたことに気づいたら、できるだけ早く再撮影することが大切です。施工がすでに進んでいる場合でも、現場に手を加えられていない部分や工事の一部を写真に残せる場合があります。
例えば、着工前の写真を撮り忘れてしまった場合に、工事が進んだ後でも写真を撮影することで証拠の一部として役立つ場合もあります。再撮影する際には、証拠能力を高めるためにも、撮影日時や再撮影の理由を記録しておきましょう。
また、元の状態に戻せる段階であれば、作業の手戻りが発生しても再撮影した方がよい場合もあります。作業の手戻りによって工程が遅れる可能性があるものの、施工完了後に発注者や監督者に指摘されて再施工するよりコストを抑えられます。
撮り忘れた写真の内容を記録しておく
工事写真を撮り忘れた場合は、後からでもわかるように撮り忘れた写真の内容を記録しておきましょう。
内容を記録する際には、「撮影を忘れた理由」「どの工程の写真か」「その時点の状況説明」などを記載します。後から見ても状況の把握ができるように、工事報告書や記録書にも残しておきましょう。
関係者に連絡を入れる
工事写真の撮り忘れに気づいた際には、すぐに工事関係者や協力会社に連絡を入れましょう。
場合によっては、他の業者や関係者が写真を撮っている可能性もあるため、写真の共有ができるかもしれません。また、発注者にも連絡をして、現場を訪れた際の写真があるか確認しておくとよいでしょう。
他の手段がないか検討する
工事写真を撮り忘れた場合には、他の手段で代替できないか検討しましょう。
例えば、現場に設置している監視カメラや、作業中に撮影した動画から該当部分を切り出して証拠になる場合もあります。
また、工事前後の施工計画書や検査記録、作業日報、材料納品書、現場の記録メモなども客観的な証拠として使用できることもあります。
トラブルに備える
法律によって工事写真の提出が義務化されている工事の場合は、トラブルに備える対策も必要です。
写真の撮り忘れが原因で、契約違反や補助金の不承認、報酬の減額などに直面した場合は、法律の専門家に頼ることも検討しましょう。
特に大規模な工事や公共工事においては、大きなトラブルに発展する可能性もあるため、早めに備えることが重要です。
工事写真の撮り忘れを防ぐ方法

工事写真の撮り忘れはトラブルにつながる可能性があるため、事前に対策を行いましょう。
ここでは、工事写真の撮り忘れを防ぐ方法を解説します。
アラームやリマインダーを活用する
アラームやリマインダーを設定することも、工事写真の撮り忘れ対策として有効です。撮影予定時刻が近づいたら、スマートフォンやタブレットのカレンダーアプリやタスクでアラームやリマインダーを設定しましょう。
撮影時間に通知が届くようにすることで、担当者は工事写真の撮り忘れを防ぐことができます。
撮影担当者を決める
工事写真の撮り忘れを防ぐためには、撮影責任者を設定し、その担当者が撮影計画から実施までの管理を行うことが望ましいです。
撮影担当者は、工事計画書や進行スケジュールをもとに、撮影タイミングを計画します。また、問題が発生した場合にはその状況を記録し、撮影を担当した社員を正しく管理してすぐに提出できるようにしておくことも大切です。撮影の責任者を明確にすることで、役割分担を明確にし、撮影漏れや誰も撮っていない事態を防げます。撮影した写真の整理や保存も責任者が行うことで写真の紛失を防ぎ、トラブル発生時の迅速な対応にもつながるでしょう。
工事着手前に撮影計画を策定する
工事写真の撮り忘れを防ぐためには、工事開始前に撮影計画を立てることがポイントです。事前に着工前、施工中、完了後の各段階において、どの箇所を撮影するかリストアップしましょう。
特に基礎工事や隠蔽部分に関しては工事が進むと再撮影が難しくなるため、撮り忘れを防ぐ重点ポイントです。
リストに基づいて撮影を進めていくことで、必要な写真の撮り忘れを防げます。
また、作業計画書で事前に撮影計画を共有しておくことで、作業と撮影の両方を同時に進めることができます。
チェックリストを作成する
工事写真の撮り忘れを防ぐためには、撮影チェックリストを作成し、現場で確認しながら進めていくのがよいでしょう。
工事が始まる前に、「いつ・どこで・どの箇所の写真を撮るか」をリストアップし、着工前、施工中、完了後の各段階で必要な写真を明確にします。これにより、撮影漏れを防ぎ、重要な工程や使用材料の記録を残すことも可能です。
チェックリストの作成や共有は、施工管理クラウドシステムがおすすめです。例えば、『Photoruction (フォトラクション)』では、タスクや図面に関連付けてメモやチェックリストを作成・共有できます。チェックリストはクラウド上で共有できるため、リアルタイムに情報共有が可能です。
施工管理クラウドアプリを活用する
工事写真の撮り忘れを防ぐためには、施工管理クラウドアプリの活用もおすすめです。
クラウド上で案件の情報を管理・共有できるツールで、撮影した現場写真を担当者間で共有できる機能もあります。これにより、進捗状況や撮り忘れをその場で確認できるようになり、写真の保管や取り出しもスムーズです。
例えば、『Photoruction (フォトラクション)』では、現場・工程ごとに必要な写真のリストやタスクを設定できます。これにより、どのタイミングで写真を撮影すべきかが明確になり、撮り忘れの防止につながります。
撮影した写真はリアルタイムでクラウドにアップロードされ、関係者全員が即時に確認することも可能です。複数人で同じ台帳を編集できるため、担当者の撮り忘れも気づきやすくなります。
また、工程表や検査項目と連動し、必要な写真撮影を自動でリマインドすることもできます。
まとめ
工事写真の撮影と管理は、工事の品質証明や安全性の確認のために欠かせません。
工事写真を撮り忘れてしまうと、発注者との信頼関係が低下し、補助金申請が却下される可能性もあります。そうならないためにも、工事写真を適切に管理し、撮り忘れを未然に防ぐことが大切です。
工事写真の撮り忘れを防止し、効率よく管理するためには施工管理クラウドアプリをおすすめします。
株式会社フォトラクションが提供する『Photoruction』は、工事写真の撮り忘れ防止に有効な機能も多く取り揃えている施工管理クラウドアプリです。
クラウド共有によるチェックリストやタスク管理、写真の自動整理などの機能を通じ、工事写真の撮り忘れを防止し、生産性の向上やトラブル防止につなげます。
サポート体制やセキュリティ対策も充実しているため安心して導入いただけます。まずは無料ダウンロードできるサービス紹介資料をご覧ください。


